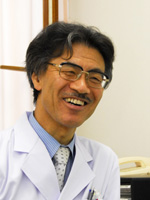第3章食事の話 第1節 実は食事が治療と予防のポイントであること3項・「食事」による認知症のリハビリ
「食事」という行動の認識付け
認知症では食事との認識が崩れて、盛り付けをグチャグチャに崩して食べられるという問題が出てきます。
皆さんが有してられる食事への美意識や、尊いものをいただくという感謝の念が消え去り、モノとしての扱いに変わる行動です。これが驚きとして周りのヒトに認知症ではなかろうかという疑問をいだかせます。
食事動作で、これは大きな兆候となります。これが出現すれば、認知症は進行した状態と思われます。
認知症への予防として、食事動作の継続と食べるものという意識付けは重要になり、運動機能リハビリと認知機能維持として意味があります。
出来るだけ長くお箸を使って物を挟む、摘みあげる、ナイフとフォークを使って食べる、熱いものをフーフーと吹いて冷ます、モノをすする、いろいろな硬さ崩れやすさの食材を噛んで咀嚼して、飲み込み嚥下するのは大事な認知症予防のリハビリになります。
よく噛むことは、誤嚥防止の大切なリハビリ
自歯があるのは意味があり、固いものでもしっかりと噛めます。それにより、咀嚼の筋活動は脳の覚醒度を刺激する入力となり、誤嚥の可能性は少なくなります。
食行動でこの咀嚼は、誤嚥防止の大切なリハビリとなります。
眠気覚ましにガムをよく噛みますが、これと同じに食行動でモノを噛む、咀嚼することが眠気を予防してしっかり覚醒し、飲み込むときに誤嚥防止となるわけです。
認知症では、怒りや暴言、暴力行為の改善に種々の薬剤使用から、傾眠状態となられることが多いです。そのため、覚醒度不十分なままでの食事となり、誤嚥される危険性も増えます。
このように食べるときの状態も大切です。その時の誤嚥の危険性を回避するためにも、しっかりと噛む行為を行うのは大事です。
噛めるためには、歯の手入れは欠かせませんし、良い入歯も大事です。患者さんを診るときも、自歯か否かを知ることは、誤嚥防止の最初の一歩です。
日頃の歯磨きや歯の手入れは、すぐに始められ、認知症での誤嚥防止につながります。
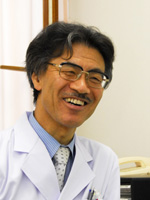
占部 新治(うらべ しんじ)
- 経歴
-
- 1976年
- 北海道大学 医学部 医学科卒業
- 1980年
- 北海道大学 大学院 医学研究科生理系修了 医学博士
- 1980年
- 北海道大学 大学院 医学研究科生理系修了 医学博士
- 1981年
- 北海道大学 医療技術短期大学部 理学療法学科 助教授
(現:北海道大学 医学部 保健学科)
- 1995年
- 札幌医科大学 精神医学講座 講師 外来医長
- 1999年
- 札幌医科大学 保健医療学部 作業療法学科 教授
- 2001年
- 札幌医科大学 大学院 保健医療科学研究院 教授
- 2007年
- 北海道大学 大学院 保健科学研究院 教授
- 2011年
- 京都 三幸会 北山病院 副院長
- 2013年
- 京都 三幸会 第二北山病院 副院長 現在に至る
- 専攻領域
- 精神医学、 神経科学、 リハビリテーション医学
- 主な著訳書
- 日経サイエンス「 運動の脳内機構」 E.V.Everts著
- 主な著書
- 臨床精神医学講座 S9 アルツハイマー病(中山書店)、精神医学 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野(医学書院)、「学生のための精神医学」(医歯薬出版)
- 所属学会
-
- 精神神経学会 専門医、専門指導医
- 老年精神医学会専門医、専門指導医
- 認知症学会専門医、指導医
- リハビリテーション医学会 臨床認定医
一覧へ戻る