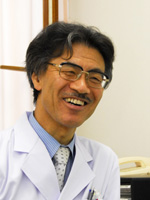第4章 環境の話 第1節 家庭環境1項・家庭の中に隠れている要因がある
会話の減少と感情情動の衰退
先ず、家庭環境こそ、この数十年の間に一気に変化した身近な出来事なのです。
第一番目に、家族構成が3世代から2世代そして1世代へと縮小し、1世帯の人数は、祖父母、両親、兄弟の6〜7人から4人、そして2人、1人と減少してきました。これにより、高齢者は2人または単身生活者が激増し、会話も減って、1週間に1人としか会話をしない人は日本では高齢者の15%に上り、この数字は増えています。欧米では7~8%ですから、日本の高齢者は一人暮らしで他人との会話がない方が多く、増えています。会話の減少はとりもなおさず、認知症への道を歩んでいくことを意味します。ヒトである由縁の言語機能の未使用は、思考機能と疎通能力の低下を招き、記憶やワーキングメモリーを使うことも無くなり、廃用性の機能低下となり、言語使用によるコミュニケーション欠乏、そして笑う、悲しむ、憤る、共感するという会話で生じる感情、情動が生活から消えていきます。話して聞くという直接言語の消失は、ヒトらしい感情情動の世界が衰退していくことなのです。
家庭内での問題解決能力の低下
また、同じ屋根の下で暮らすことは、ぶつかる状況も多く、それを解決するために対話が必要となり、時間的や場所的な譲り合い、協力をすることを決めることになり、コミュニケーションの増加と理解能力、そしてそれを守って実行する責任の機能が育ちますが、これらをしなくなるために、そうした能力低下は、たちまち社会性機能の衰退となり、認知症症状を呈することになります。こうして、認知症は身近な家族の構成変化による家庭環境変化から、徐々に始まってきています。自分一人の気ままさから、こうした能力低下と不安や淋しさを失って認知症への坂道を転がり始めているのです。ご近所の問題は「第2節 社会環境」でお話します。
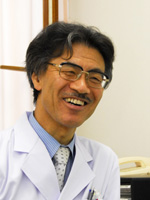
占部 新治(うらべ しんじ)
- 経歴
-
- 1976年
- 北海道大学 医学部 医学科卒業
- 1980年
- 北海道大学 大学院 医学研究科生理系修了 医学博士
- 1980年
- 北海道大学 大学院 医学研究科生理系修了 医学博士
- 1981年
- 北海道大学 医療技術短期大学部 理学療法学科 助教授
(現:北海道大学 医学部 保健学科)
- 1995年
- 札幌医科大学 精神医学講座 講師 外来医長
- 1999年
- 札幌医科大学 保健医療学部 作業療法学科 教授
- 2001年
- 札幌医科大学 大学院 保健医療科学研究院 教授
- 2007年
- 北海道大学 大学院 保健科学研究院 教授
- 2011年
- 京都 三幸会 北山病院 副院長
- 2013年
- 京都 三幸会 第二北山病院 副院長 現在に至る
- 専攻領域
- 精神医学、 神経科学、 リハビリテーション医学
- 主な著訳書
- 日経サイエンス「 運動の脳内機構」 E.V.Everts著
- 主な著書
- 臨床精神医学講座 S9 アルツハイマー病(中山書店)、精神医学 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野(医学書院)、「学生のための精神医学」(医歯薬出版)
- 所属学会
-
- 精神神経学会 専門医、専門指導医
- 老年精神医学会専門医、専門指導医
- 認知症学会専門医、指導医
- リハビリテーション医学会 臨床認定医
一覧へ戻る